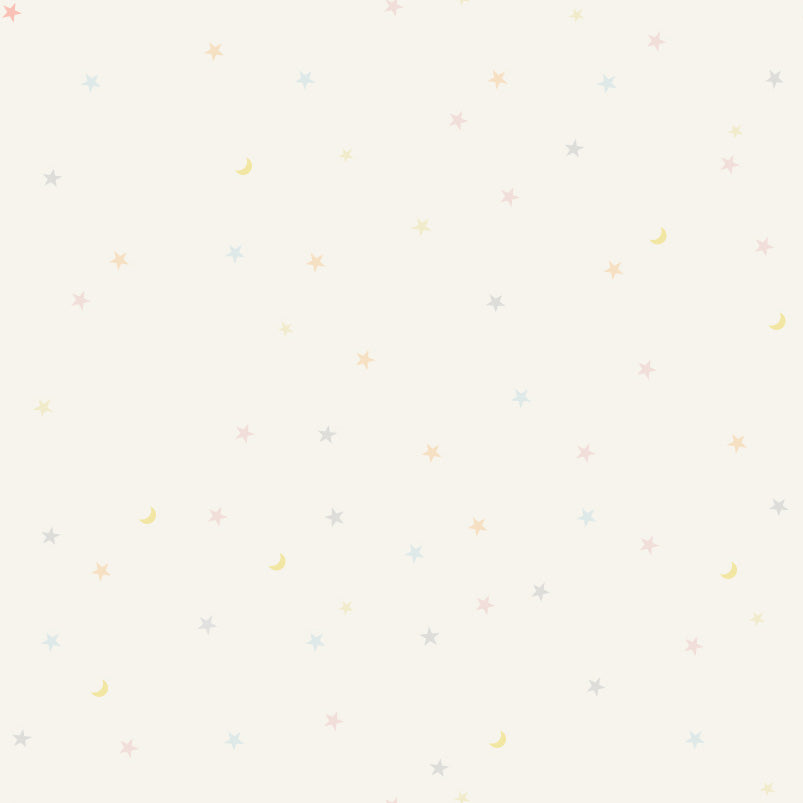「ねんトレ」と聞くと、どんなイメージがありますか?
「😣泣かせるのはかわいそう...」
「😓うちの子はそもそも寝ない子だから、、」
「😵分単位のスケジュール管理が大変そう」
👆こんなふうに思ってたらちょっと待って❗️❗️
それって実は勘違いかも⁉
今回は、ねんトレの正しい知識と方法を紹介します🌟
「ねんトレ気になっているけど、ハードルが高そう🥲」と感じているママは、ぜひ最後まで読んでくださいね♡
ねんねトレーニングとは
ねんねトレーニングとは、『赤ちゃんの寝る力を引き出し、ひとりで寝る習慣をつけるための練習。』
赤ちゃんは誰でも寝る力をもっています💪🌟
“うちの子は寝ない子”と思い込んだままなのは、すご〜くもったいないです!
赤ちゃん・子どもが自力で落ち着き、1人で寝られるようにママ(パパ)が誘導してサポートするトレーニングが「ねんねトレーニング」です!
☘️ねんトレのメリット
🌟子どものメリット
- 夜泣きや夜間授乳の回数が減少
- 眠りが深くなる
- 成長ホルモンが十分に分泌される
- 生活リズムが整う
- 日中の機嫌がよくなる
🌟ママ(パパ)にとってのメリット
- ママパパもぐっすり夜通し眠れる
- イライラせず機嫌がよくなる
- 産後うつの発症リスクが下がる
家族全体の笑顔が増え、「生活の質」があがります!
😴ねんトレを始めるタイミング
以下の項目に、1つでも当てはまるときは、ねんトレを検討してみてね!
✅生後6か月以降で夜間覚醒が3回以上 or 夜中に60分以上覚醒している
✅寝かしつけるのにイライラする
✅ママ(パパ)の睡眠が十分にとれていない
✅1日中子どもがずっと眠そうで機嫌が悪い
✅1歳すぎても夜中に頻回に起きている
✅幼児で習慣的に夜の入眠時間が22時を超えている
それでは具体的に、ねんトレの方法を紹介していきます!
ねんトレの方法
ねんトレの方法は複数あるので、お子さんの性格やママ(パパ)の性格に合った方法を選ぶのがベスト!
😴主なねんトレの種類
-
フェイドアウト
- 徐々に赤ちゃんとの距離をとる方法
-
タイムメソッド
- 徐々に離れる時間を伸ばしていく方法
-
エクスティンクション
- 泣いてもとにかく見守り続ける方法
-
ジーナ式
- スケジュールを厳格に守る方法
様々な種類がありますが、私は、フェイドアウトメソッド・タイムメソッドの2種類を、おすすめしています!
ジーナ式は、日本では有名ですが、医学的な根拠は確認されていません!
とはいえ、お子さんに合うなら取り入れてもOKです♪
ねんトレにはさまざまな方法がありますが、お子さんやご家庭に合ったメソッドを選ぶことが大切です✨
「フェイドアウトメソッド」の具体的な方法や、成功のポイントなどについて、詳しく解説していきます😊
フェイドアウトメソッドとは
この方法は、子どもを見守りながら少しずつ距離を離していくことで、安心して眠りに誘導するメソッド。
フェイドアウトメソッドは、子どもを見守る「距離」を、約2週間かけて徐々に広げていく方法です👶
子どもを1人にせず、寝るまでの間ずっとサポートができるため、安心して眠りにつくことができます😴
⭐️フェイドアウトメソッドのデメリット
- セルフねんね習得までに時間がかかる⏰
- 目の前で泣かれるので親が辛くなる🤦♀️
- 下の子がいる場合は難しい👶
このメソッドのデメリットとしては、セルフねんねを習得するまでに時間がかかることがあります😌また、目の前で泣かれることがあるため、親にとっては辛いと感じることも。
さらに、下の子がいる場合は実践が難しいかもしれません。
それでも、根気よく続けることで、効果が期待できる方法です👍
次は、やり方を解説しますね!🌸
フェイドアウトメソッドのやり方
ねんトレは、夜の就寝時から始めるのがポイントです。
以下の手順で行ってみましょう😊
①ねんねルーティンを行う🌙
月齢に応じた活動時間内に、毎晩同じ流れでルーティンを行います。これにより、子どもが寝る時間だと理解しやすくなります⏰
②ねんねルーティンの最後に
子どもが起きていて目が開いている状態で、ベビーベッドに優しく置きます。この際、安全な睡眠環境を整えておくことが非常に重要です🛏️
③子どもを見守る👀
ママ・パパ・保育者は、トレーニング日数に応じた距離で子どもを見守ります。
初日はすぐそばに座り、徐々に距離を離していきましょう👌
続いて、お子さんの寝床との距離について、詳しく解説しますね👇
トレーニング日数と座る場所
日を追うごとに、少しずつ、お子さんの寝床との距離を伸ばして離していきましょう🌱
-
1~3日目:お子さんのすぐ隣
-
4~6日目:お子さんの寝床と寝室のドアの中間
-
7~9日目:寝室のドアの前
-
10~12日目:寝室のドアを少し開け、 親の姿が見えるようにしたドアの外
-
13~14日目:寝室のドアを閉めて、部屋の外
😭激しく泣いているとき
いつもと違う寝かしつけに、お子さんが戸惑ってしまうのは当然のこと。
激しく泣いてしまうお子さんもいるでしょう。
そんな時は段階的にあやしていきましょう😊
①「大丈夫だよ、ママ(パパ)はここにいるからね」と声をかけます。
↓それでも泣いている場合
②トントンします。
↓さらに泣いている場合
③抱っこしてもOK!
※ただし、トントンや抱っこをしながら寝かしつけるのはNG⚠️
↓
④泣きが落ち着いたら、寝床に戻します。
⑤完全に寝るまで、何もせずに座って見守ってください。
⑥完全に寝入ったら、さらに10~15分見守り、そのあと部屋を出る
⑦夜中に起きたらママ(パパ)は、その日の座る場所に戻り、寝かしつけのときと同じ方法であやしてください。
あとでママ(パパ)が赤ちゃんと同じ寝室で眠る場合、
入室時にドアの隙間から、光や音が入らないよう注意してくださいね❗️
なるべく抱っこまではいかないで!!
難しいと感じた場合は、タイムメソッドに切り替えましょう👍😊
⏰タイムメソッドとは
決められた「時間」の間隔で部屋に入って、決められた「時間」子どもをあやし、部屋を出て、見守る方法です⏰
この方法では、具体的な時間が決まっているため、シンプルで実践しやすく、子どもの泣きがおさまるのが早いと言われています😊
タイムメゾットのデメリット🙅♀️
- 泣いているのに部屋を出るので、親が辛くなることも
- 子どもの泣きが激しくなる場合がある
続いて、やり方を解説していきますね!🌸
タイムメソッドが向いてる家族
まずはタイムメソッドが向いているか、チェックしてみましょう👇
✅ママパパのチェックリスト
□子どもの泣いている姿に弱く、たえられない
□難しいことは苦手
□シンプルな方法がいい
✅お子さんのチェックリスト
□目の前に親がいると興奮する
□2人以上いる
当てはまる項目が多ければ多いほど、タイムメソッドに向いていると言えます😉
「どれがいいかわからない💦」と悩んでいる方は、"フェイドアウトメソッド"から始めると◎
タイムメソッドのやり方
ねんトレは、夜の就寝時から始めるのがポイントです💡
以下の手順で行ってみましょう😊
- 子どもが目が開いている状態で、ベビーベッドや布団に置く🛏️
- 保育者は部屋を出て、子どもが泣いてもすぐに部屋に入らず待機時間を守る⏰
- 1週間かけて部屋に入るまでの時間をだんだん伸ばしていき、子どもが一人で寝られるよう見守る👀
続いて、トレーニング日数と待機時間について、詳しく解説しますね👇
トレーニング日数と待機時間
トレーニング日数に応じて、部屋の外での待機時間を伸ばしていきます⌛
激しく泣いている場合のみ、入室(あやす)→退室→待機を繰り返します👌
入室後は、1分以内に退室しましょう🏃♀️💨
タイムメソッドの進め方
以下の手順を参考にしてください🌸!
💡ねんトレ成功のポイント
ねんトレを成功させるためには、以下のポイントが重要です!
- 睡眠の土台が整っていること
- 一貫性もってを続けられること
- 保育者のやり抜く力があること
1つ目の「睡眠の土台が整っていること」は必須条件です❗️
🌙睡眠の土台とは
-
睡眠の環境を整える🌡️
- 光、音、室温の調整が出来ているか確認しましょう。
-
ルーティン🗒️
- ねんねのルーティンを繰り返しましょう
-
幸福度💗
- ママとお子さんの心の安定が大切です
質問1:ねんトレって"トラウマ"にならないの?
世界各地で、ねんねトレーニングの効果や、その影響に関する研究が行われています。
その結果から、乳幼児の睡眠問題に対して、科学的に効果があるねんねトレーニングが長期にわたって、トラウマなどのストレスにはならない。ということが証明されています!👌
正しく実践すれば、ネントレは、効果と安全性が科学的に証明されているので、安心して取り組んでくださいね◎
質問2:今日からネントレをやってもいい?
答えは、ノーです!🙅♀️
まず準備として、睡眠の土台を整えることから始めましょう!
睡眠の土台は主にこの3点🔽
- 睡眠環境を整える
- ねんねルーティンをつくる
- 親子の幸福度を高める
ネントレ開始の事前準備である、睡眠の土台を整えるだけで、ねんね改善ができたという声も多く聞きます!😊
睡眠の土台については私の著書でも
詳しく解説しています💕
ねんねトレーニングいつから始める?専門家が教える!ねんトレ攻略ガイド🌸まとめ
- ねんねトレーニングとは
- ひとりで寝る習慣をつけるための練習
- ねんトレの方法は複数!合った方法を選ぼう👍
-
ねんトレ成功のポイント
-
睡眠の土台が整っていることが大事
-
一貫性をもって続けること
-
保育者のやり抜く気持ちがある状態
-
お子さんが体調を崩しているときは、無理せずにねんトレを中断しましょう😊
回復して落ち着いたら、また挑戦してくださいね👌
- Instagramでも随時ねんね情報配信中♪
- ねんねに限らず、子育て全般のお悩みは愛波子育てコミュニティで気軽にプロに相談できるので頼ってくださいね♡